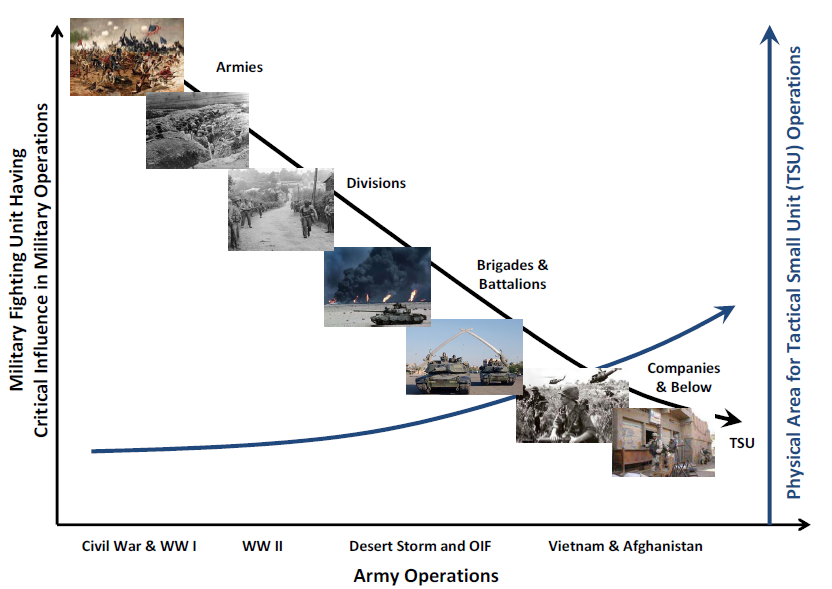2023年4月28日「ロシア兵の戦死者の半数は適切な応急処置、治療がなされなかったせい」とう記事を読んだ。その中で、『多くのロシア兵が戦場で亡くなっていますが、アルテム・カトゥリンによれば、その半数以上は即死や致命傷によるものではなく、適切な応急処置と治療を受ければ命は助かっており、適切な止血を行っていれば、手足を切断することも無かったと述べています。それはつまり、未熟な兵と応急処置に対する訓練不足、処置のためファースト・エイドキットの不足と、負傷者の搬送体制が無かったことが理由として挙げられます。Oxford Academicの発表によると事故、戦場での負傷に関わらず、外傷性による死因の35~40%が出血死によるものです。負傷した際は素早い止血と早急な輸血が生死を分けます。しかし、ロシア兵の応急処置キットは古く、ソビエト時代に作られたと思われる包帯と簡易的な止血バンドといった最低限の物しか付与されておらず、多くの兵が現代的な救急キットを持ち合わせていないことは確認されています。また、動員兵が招集された際、訓練教官が集まった兵に「銃で撃たれたら銃創にタンポンを詰めて止血しろ」と言っている様子が撮影されており、上級兵でさえも応急処置の知識、訓練が不足していることが伺えます。例え止血できたとしても、輸血は必要であり、長時間止血すれば手足が壊死してしまうので、早急に後方に搬送し、治療が必要です。しかし、ロシア軍はこの搬送体制も整備されていないとされています。侵攻する側のロシア軍ではありますが、ウクライナとは陸続きであり、現在は国境に近い東部で戦闘を行っており、決して兵站ルートが長いわけではありませんが、拠点から50km離れると補給が困窮すると言われています。』そこで、露軍の戦傷医療について、文献上の考察をしてみた。
ロシアにも戦傷の研究がないわけではない。ロシアのMirzeabassov等は、防弾服着用時の防弾背面鈍的胸部外傷(Behind Armour Blunt Trauma)の疫学調査を行っている(Mirzeabassov, T. , et. al : Further investigataion of modelling for bulletproof vest, Personel Armor Safety Symposium, Colchester, UK, 2000)。ソビエトのアフガン侵攻時、1.25mmと6.5mmのチタニウム板を用いた防弾服を着用し胸部を撃たれた17人の軍人を対象とした。武器は7.71mmEnfieldもしくは7.62mmAKM。胸部外傷のレベルとしてレベルⅠ(皮膚の擦過傷、点状出血、皮下血種、局所の血胸)からⅣ(内臓破裂・挫傷、脊椎損傷)、交戦性と胸部外傷との関係をレベルⅠ(1から3分交戦不可能、15分間の交戦制限、24時間以内に回復)からⅣ(即死、合併症死、生存者の戦意喪失)に分類した。
しかし、この疫学的データを理解する時に、アフガニスタンにおける戦争からも検討する必要がある。つまり、アフガニスタンでは、90%以上の負傷者が航空後送されたが、たった4%が中央軍病院に6時間以内に搬送されたのみであった。すなわち、病院到着前に死亡していたことになる。重傷は遅れた治療により致命的になる。戦傷治療はソビエトと米欧では著しく異なると指摘している。
以上から、露軍の戦傷医療が現場における処置だけではなく、後送も含めた治療戦略、すなわち、全軍的なTCCC(Tactical Combat Casualty Care)がないと推測される。
我国も今回のロシアのウクライナ侵攻に関して、防弾チョッキを提供したとの報道があった。ここで考えるべきことは、この防弾チョッキにおけるBABT発生に関する資料提供も行われたか否かが重要である。防弾チョッキは万能ではなく、性能の限界を知って初めて有効になる。