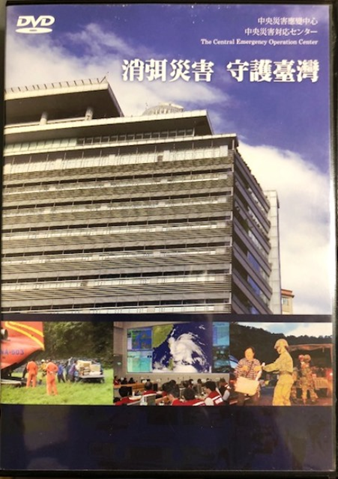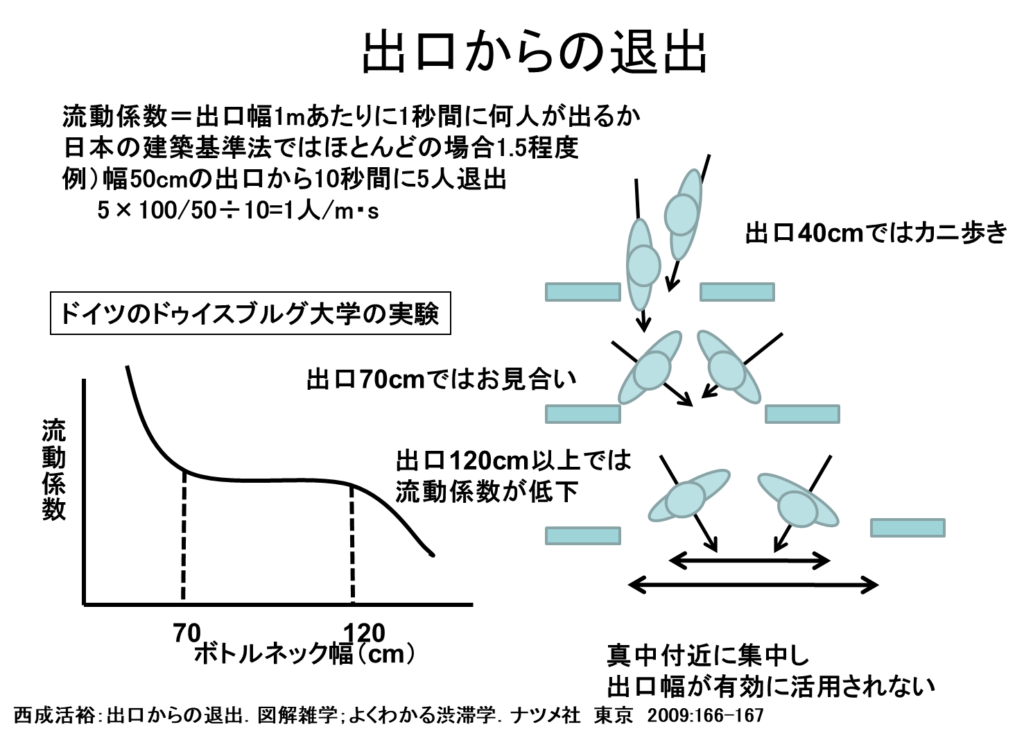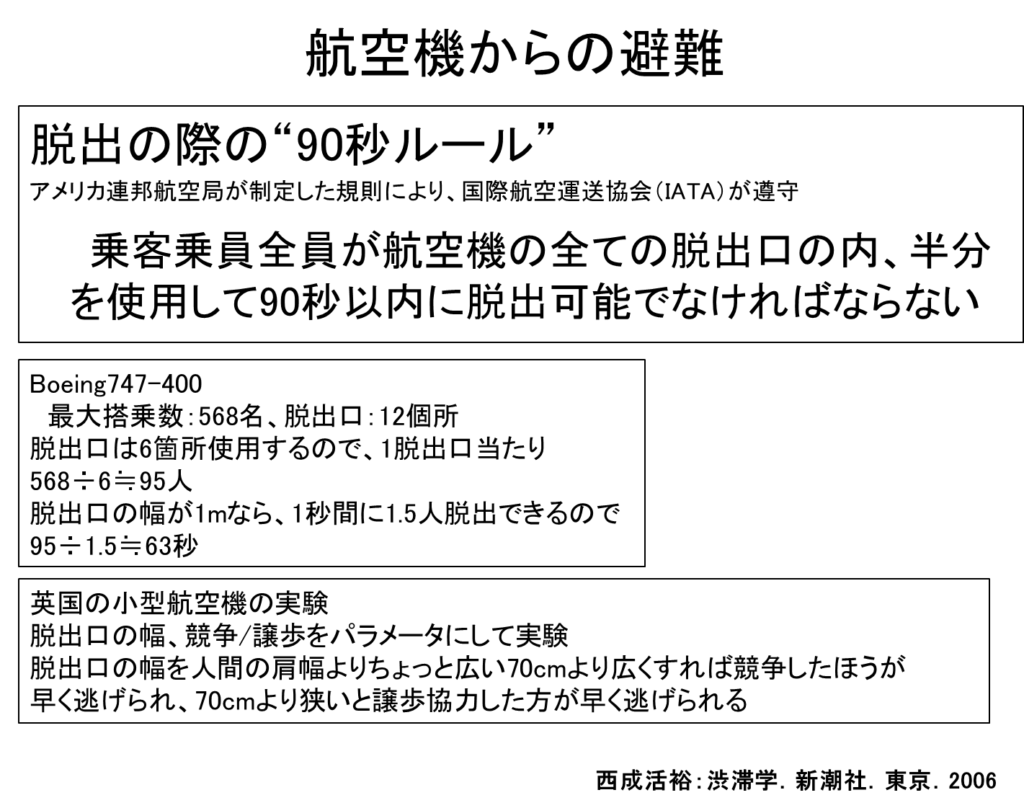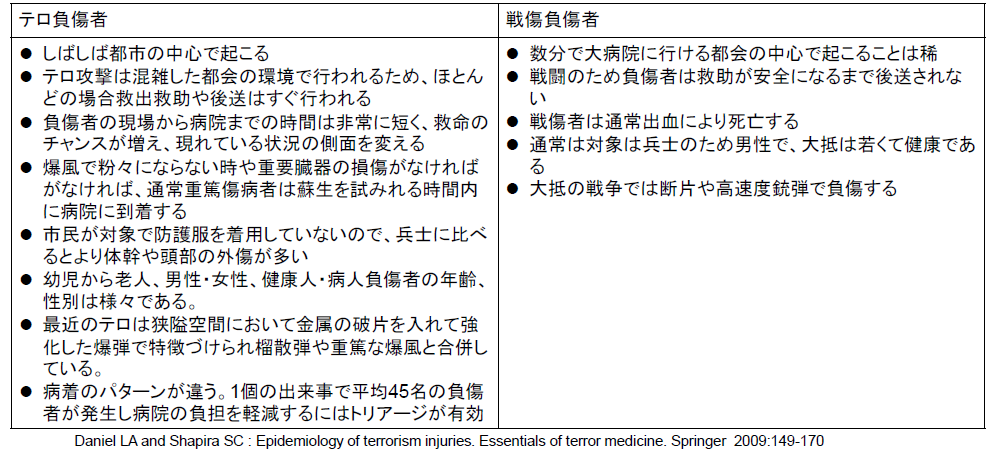『防衛医科大学校医学科は、将来、医師である幹部自衛官として必要な人格及び識見を養い、また自衛隊医官に対して自衛隊の任務遂行に必要な医学についての高度の理論、応用についての知識と、これらに関する研究能力を修得させるほか、臨床についての教育訓練を行うことを目的として設立されました。』と防衛医科大学校のHPに記載されている。
しかしながら、防衛医科大学校設立の目的は、第65回国会衆議院内閣委員会第8号昭和46年3月16日を読みとく限り、自衛隊医官の充足医対策であったようである。以下、この目的を読みとくための第65回国会衆議院内閣委員会第8号昭和46年3月16日の必要部分を掲載してある。
第65回国会衆議院内閣委員会第8号昭和46年3月16日において、鈴木一男政府委員は『自衛隊の医官は、御案内のごとく非常に不足いたしておりまして、私どもは、わが国全体の立場から考えましても、防衛庁は医官の確保の面で見ますと社会的僻地と考えておりますが、そういう面でやはり抜本的に医師の絶対数をふやすという立場に立ちまして、この際大学をつくって絶対数をふやし、歩どまりをよくしていきたいというふうなことを考えておるわけでございます。御案内のごとく、現在までに防衛庁がとっております医官の充足対策といたしましては、貸費学生制度、これは現行月額六千円になっておりますが、その他人事、処遇の改善、医療施設の近代化並びに航空自衛隊の航空医学実験隊というものが立川にありますが、これらの整備拡充並びに海上自衛隊の潜水医学実験部が横須賀にございますが、これらの整備拡充につとめて医官の定着をはかってまいりたいと思っておるわけでございますが、いままでの諸施策ではなかなか医師が定着しないし、また集まってこないというようなことで、やはり独自な絶対数確保の立場で防衛庁所管の医科大学をつくってまいりたい、このような構想を持っておる次第であります。』東中光雄委員『自衛隊の医官不足をなくしていって定着させる目的だということですから、そこで構想されておる防衛医科大学校の卒業者は、自衛隊に勤務することを義務づけるということは、これは設立しようとされている趣旨からいって当然そうなると思うのですが、そういう構想ですね。』東中光雄委員『中曽根防衛庁長官が、いろいろ検討し、各省とも折衝した結果、各種学校としての防衛医科大学校をつくりたいと考える。「防衛医科大学校の卒業生が医師の国家試験を受けられるようにしなければいけない。」そういう構想で進めておるのだという答弁を参議院の内閣委員会ですが、やられたことがありますが、そういう構想は持っておられるわけですね。』東中光雄委員『大学の場合は、学校教育法の五十二条でその目的がきまっているわけであります。防衛医科大学校といわれている場合はそれからはずれるわけですから、全然目的違うわけですね。違うものとしてやはりつくっていこうという構想。』松下簾蔵委員『防衛庁のほうから、防衛庁に勤務しております医官の充足の状況から見まして、その確保のための養成機関を何らかの形でつくりたいという強い御要望があるということは伺っておりますし、私どもも承知いたしております。それをどのような形で今後実現していくかということにつきましては、先ほど防衛庁の衛生局長からもお話がありましたように、四十六年度におきまして調査費が計上されるという予定であると伺っておりますので、その段階におきまして関係各省との間にさらに詰めた協議が行なわれるであろうと考えておりまして、その過程で厚生省といたしましてもいろいろな事情を含めて十分検討いたしたい、そのように考えております。』 東中光雄委員『学校教育法にいう大学の場合は、先ほども申し上げたように、たとえば目的をこう書いていますね。「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。」、「知的、道徳的」云々となっているわけですが、防衛医科大学校という場合では、医官の確保というところから出発しているという点で、これは態様がごろりと変わってくるわけであります。しかも国民の健康にあるいは生命に直接関係のあることで、一般的な資格がそういう特殊なルートから与えられていくということになると、これは非常に大きな問題が起こってくるのではないか。特にいまお医者さんの不足というのは、防衛庁の特殊な現象ではなくて、全国的にも問題がいろいろあるわけですから、この機会にお聞きしておきたいのですが、戦後における国立、公立、私立の医科大学、医学部の設置状況これはどういうふうになっておりますか。』東中光雄委員『国全体でそれはあまりふえていない、むしろ一般の大学のふえ方から見ても非常に押えられていると思うのですが、防衛庁だけが医官不足ということじゃなくて、防衛庁に医官が集まらないというのは、それはまた別の理由があるのであって、だから別の体系の医官養成機関をつくっていくというふうなことは絶対に許されるべきじゃないというふうに私たち考えるわけです。四千三百八十、これは入学定員ですけれども、こういう状態でいまの阪大の入試問題なんかが起こってくる一つのもとがあったのじゃないかというふうにも思うわけですが、阪大の入試不正事件を契機にして、医者の養成、医科大学なり大学医学部の制度と申しますか、そういう点でどういうふうな方針なり反省なりをされておるか伺いたいと思います。』東中光雄委員『全国では無医村が三千地区ある。そこはやはり医師を要請しています。沖繩だってそうであります。そういう医師の要請があるからということで今度は医師の養成制度がどうなるかといえば、先ほどの私学の場合のように、これはとてつもない金がなければ入れないような差別が一方でやられている。機会均等が実際上奪われるような社会的不合理性が一方では露呈しておる。一方では官費で、それから給料まで出して防衛庁の医官養成をやっていく。しかもこれは明治以来の体系からはずれる体系のものとしてそういうものがつくられていく。非常に不合理なんですね。これは国民は納得しないですよ。防衛庁に医官が集まらない、定着しないというのは、その原因は何かということを追求すればいいんで、集まらないから、だから国費で特別の養成制度をつくって、しかもそれに一般の医師養成機関と同じような資格を与えていくというような、こういうやり方になると、軍事優先といいますか、必要ならば防衛庁だけは国家予算でどんどんやっていく、一般の医師の養成制度というものを体系的に変えていくようなこともやられていくということになれば、これは医師養成の教育制度を、やはり文部省として、医学校なり医科大学なり大学医学部なりを設置し、その数、要請に応じて、そういう養成制度というものは立てられておるはずなんで、その中で特殊なものだけを軍事優先的なかっこうで認めていくというのは、どうしても納得いきません。それはもう防衛庁は防衛庁の中でやっておることだから、水産大学校なんというのと性質が違うわけですね。そういう点で、ひとつこれは医学の養成制度として全般的に非常に不合理なものが露呈しておりますので、根本的に検討していただかないと困る。このことを強く要請いたしまして、私の質問を終わりたいと思います。』
では、充足率は期待通りの成果を上げたのであろうか?政府・防衛関係者の期待通りの結果であったか否かは別として、一定の成果は得られたと思われる。以下に、関係する議事録の抜粋を示した。
第71回国会参議院本会議第20号昭和48年6月15日では、①上田哲委員の発言『・・自衛隊が、学校教育法上の医科大学でない施設で、特別な目的のために医師を養成することは、医学教育の秩序を乱すものであることは疑いをいれません。これは、質の低下を招くおそれがある上に、この点について責任の所在も求められないだけでなく、特に、一般国民への利益給付は何も期待できないのであります。また、現在、自衛隊の医官は不足とは言いながらも、二百七十一人は確保されているのでありまして、これは自衛官八百五十八人に一人の割合となり、国民一般が九百二十人に一人の医師の割合の中にあるのに比べるならば、決して低い水準ではありません。また、自衛官が年間医師にかかる回数は、一般の五・八一回に対しまして、二・七回と、半分にも満たないという実態もあるのであります。ここに百九十億円の国費を投ずることは、国民全般の医師不足の実態から見て、医療行政上均衡を失する優先処置と考えなければなりませんが、厚生大臣の見解を承りたいと思います。』 ②第71回国会衆議院本会議第47号昭和48年6月28日では、中路雅弘委員の発言『第二の重要な問題点は、防衛医科大学校の設置であります。政府は、防衛医科大学校の設置は自衛隊における医官不足を補うための医官の養成だと説明していますが、その真のねらいは、中曽根元防衛庁長官の訪米報告で明らかなように、アメリカの近代軍事医学、軍医技術を吸収し、米軍援助のもとに、自衛隊による軍事医学研究者の養成及び軍事医学研究を進める体制をつくり上げることにあることは明らかであります。アメリカの近代軍事医学とは、あのベトナム、インドシナ地域において、ボール爆弾や各種の毒ガス、枯れ葉作戦などに代表されるような、残虐な殺傷に使用されたものであることは否定することのできない事実であります。防衛医科大学校の設置がアメリカ近代軍事医学、軍医技術を吸収することを目的としていることは、自衛隊が人民を殺傷するための生物化学兵器の大規模な開発と研究に踏み出すためではないかという重大な疑惑を持たざるを得ないのであります。わが党は、この点を質疑の中で指摘しましたが、政府、防衛庁は、将来どんな研究が行なわれるか、具体的な問題についての答弁をことさら避け、国民の疑惑が根拠のないものでないことを浮き立たせたのであります。また、防衛医科大学校設置が、あの戦前の軍国主義時代にさえなかった自前の医官養成、軍事医学研究体制をつくるという点でも、さらにまた、教育基本法並びに学校教育法に基づく学問・研究の自由を奪った違法なものである点でも、黙視できない重大な問題であります。』 ③第71回国会参議院内閣委員会第29号昭和48年9月18日では、鈴木一男政府委員『病院におきまする医官の状況でございますが、まず陸上自衛隊におきましては、定員百七十二名に対しまして現員が百二十八名、充足率は七四・四%であります。次に海上自衛隊におきましては、定員が三十九名に対しまして現員三十二名、充足率は八二・一%であります。次に、航空自衛隊でございますが、定員二十二名に対しまして現員十四名、充足率は六三・六%でございます。』一方、部隊におきましては、陸上自衛隊につきましては、定員四百五十二名に対しまして現員五十九名、充足率にいたしまして二一丁一%、次に海上自衛隊におきましては、定員七十三名に対しまして現員十一名、充足率一五・一%であります。航空自衛隊におきましては、定員七十八名、現員二十四名、充足率三〇・八%でございます。 ④第208回国会予算委員会第一分科会第2号(令和4年2月17日(木曜日))において、松本尚文科員の質問に対して鈴木政府参考人は『まず、医師の資格を持つ自衛官につきましては、令和三年三月三十一 日時点で、陸海空合わせて約九百九十名おります。そのうち、外科専門 医が約五十名、救急科専門医が約二十名、アキュート・ケア・サージャ リー学会認定外科医はゼロ名となっております。また、看護師の資格を有する自衛官は約千七十名おります。そのうち、 救急看護認定看護師数はゼロ名、集中ケア認定看護師数は若干名いるということになっております。また、年間のISS十五以上の重症外傷例につきまして、自衛隊中央 病院においてでございますが、正確な統計は取っておりませんが、年間 数件程度と承知しているところでございます。』
1974年の開校から2023年現在までの卒業生総数のデータはないが、自衛医官は1973年の271名から2021年約990名と約719名、48年間に719名増えた勘定になる。単純計算では毎年約15名増加してきたことになる。この数字が期待された数値であるとは到底思えないが、自衛隊医官の定着に関する有効な手段は示されていないと思われる。また、新たに防衛医科大学校に戦傷医療センターなるものが設置されるというが、戦傷には外科系医師が多数必要であるはずが、令和三年三月三十一 日時点で、陸海空合わせて約九百九十名、うち、外科専門 医が約五十名、救急科専門医が約二十名、アキュート・ケア・サージャ リー学会認定外科医はゼロ名という体制で本当に戦傷医療に対応可能なのか、はなはだ疑問が残るのは私だけであろうか?
医学教育第18巻第1号1987年2月防衛医科大学校副校長医学教育部長高谷 治著「わが国におけるプライマリ(ヘルス)ケアの卒前教育の先導的試行」において、建学の精神として以下のように記載されている。『約15年前に防衛庁として独自の医大が必要であるかどうかについて、故武見太郎先生を委員長として9人の医学界等の学識経験者からなる大臣に対する特別諮問委員会(懇談会)ができ、検討の結果の答申に基づいて設立されることとなったのが防衛医大であるが、その答申の内容の医学教育に関係する部分の大略は以下のとおりである。すなわち、「新しい時代における医療とそれに即応した医療教育のあり方について、問題点の十分な認識のもとに、従来の医師養成のあり方に対する反省の上で現在の医師養成の長所を取り入れるとともに、将来の医療のビジョンを考え、新しい見地からその養成を図ることが適切と考えられ、人格、識見ともにすぐれた有能な総合臨床医の育成を目標として医学教育を実施すべきである。ここでいう総合臨床医とは、一般内科一般外科を基礎とし、人間の健康,疾病に関与する肉体的のみならず、心理的、社会的要因までも理解できるように幅広く訓練され、単独に、あるいはグループ・プラクティスの一員として総合医療を適用できる知識と能力をもつ医師を意味する。さらにその上で医学の本質に則り、専門領域に関する高度の医学研究の遂行が卒業生においてできうるよう必要な方途を講ずるべきである。」としている。これをいいかえれば、従来の医学臨床教育の反省を加味して将来の一般的国民医療のニーズに答えるため、従来の文部省系医科大学の医学教育に加えて総合臨床教育を行い、総合臨床医プラス専門医を作ることが、ひいては自衛隊現状のニーズに答え、また災害等の非常事態にも備えての医療の必要に応じうることとなるという考え方である。』すなわち、1987年の時点では防衛医科大学校は「従来の文部省系医科大学の医学教育に加えて総合臨床教育を行い、総合臨床医プラス専門医を作ること」の精神に基づいて教育を行ったいたと思われる。このプライマリーケアを育成する方針では、どう考えても戦傷医療には対応できないと思われるが、いつの時点から、防衛医科大学校は戦傷医療のスペシャリストになったのであろう?ご存じの方がいれば、是非教えて頂きたい。